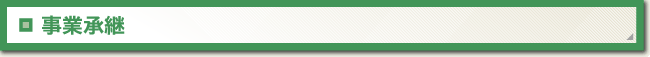

皆様の中には、事業を会社化して経営なさっておられる方もいらっしゃるでしょう。
その事業を次の世代へと円満に引き継ぐためには、以下で述べるように、民法上の「遺留分」に関する規定を考慮しておく必要があります。
以下、順を追って御説明致します。
民法には、相続に関して、「遺留分」というものが定められています。この「遺留分」というのは、亡くなった方の相続人(ただし、兄弟姉妹は除きます。)が有する、いわば相続に対する期待権と考えて頂ければよいと思います。
例えば、ある人(X)(配偶者は既に亡くなっているとします。)に子が2人いるとして、Xが、全財産を、一方の子(A)に相続させるという遺言を残して亡くなったとします。この場合、もう一方の子(B)は、自分にも一定の割合(この例の場合ですと、1/4です。)の財産を取得させて欲しいと請求することができます(「遺留分減殺請求」といいます。)。
この様な制度が定められているのは、上記の例で言うと、Aに自分の全財産を取得させたいというXの意思と、相続に対するBの期待権の調和を図るためであり、それ自体には合理性があるといえます。
とはいえ、事業承継の場面では、この「遺留分」に関する規定が障害になってしまうことがあるのです。
前記の例で、Xが会社を経営していたとします。そしてXは、子A、Bの内、Aに、自分の営む会社を承継させたいと考えたとします。そのまま何も手を打たなければ、会社の株式等や、会社の事業に用いている資産(土地、建物等)が1/2ずつ、A、Bに相続されてしまいますので、Xは、生きている内に、それら株式等や資産をAに生前贈与したとします。間もなくXは亡くなったとします。
Xがここまで手を打ったとしても、Bには、先程述べた「遺留分減債請求権」というものがありますので、Bがこれを行使すれば、株式等や資産は、AとBの共有になってしまいます(Aが3/4、Bが1/4です。)。そして、この共有の状態を解消するためには(Aが株式等や資産の全てを取得するためには)、改めてA、B間での協議や法的手続が必要となってしまうのです。これでは、Aへの円満な事業承継を考えていたXの意図に反することになりますし、ひいては事業の経営に悪影響を及ぼしかねません。
そこで、遺留分に関して、民法の特例を定める「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下本稿では「特例法」と表記します。)が制定・施行されたのです。
この特例法によって、一定の用件を満たす後継者は、遺留分権利者全員との合意及び所定の手続(経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可)を経て、⑴生前贈与株式を遺留分の対象から除外すること、⑵生前贈与株式の評価額を予め固定することが認められるようになりました。
円満な事業承継のために、この特例法の制度を利用することが検討に値します。

とはいえ、この特例法の内容は若干複雑です(下記御参照)。
特例法を利用した円満な事業承継をお考えの方は、まずは当事務所に御相談頂きたいと思います。
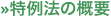
遺留分に関する民法の特例の対象は、3年以上事業を継続している会社であって、⑴製造業にあっては資本金が3億円以下又は従業員数が300人以下、⑵卸売業にあっては資本金が1億円以下又は従業員数が100人以下、⑶小売業にあっては資本金が5,000万円以下又は従業員数が50人以下、⑷サービス業にあっては資本金が5,000万円以下又は従業員数が100人以下の規模のものです。
これらの会社の代表者又は代表者であった者が、その推定相続人である後継者(その会社の株式等の議決権の過半数を有し、かつ代表者として経営に従事していることが必要です。)に対してその会社の株式又は持分(以下本稿では併せて単に「株式」と表記します。)や事業用資産を生前贈与した場合に、当該特例の適用を受けることができます。
株式を生前贈与した場合、原則としてその贈与は遺留分減殺の対象となることから、減殺請求がなされることによって株式が分散し、会社の意思決定に支障を及ぼす可能性が生じます。
しかし、遺留分に関する民法の特例を利用すれば、推定相続人全員の合意により、生前贈与株式を遺留分の対象から除外することが認められます。
これによって、相続に伴って株式が分散し、会社の意思決定に支障が生じるリスクを予め排除することができるようになります。
株式の生前贈与に対して遺留分減殺請求権が行使された場合、遺留分算定の基礎財産に算入すべき株式の価額は、原則として相続開始時点の評価額で算定されます。すなわち、株式の価値が、生前贈与後の後継者の貢献により上昇したとしても、遺留分の算定に際しては後継者の貢献を考慮することなく上昇後の評価で算定されます。
しかし、遺留分に関する民法の特例を利用すれば、推定相続人全員の合意により、生前贈与株式の評価額を予め相当な価額(価額の相当性について弁護士、公認会計士等の証明を受けることが必要です。)に固定することが認められます。
これによって、後継者は株式等の価値が上昇することに伴う将来の遺留分額の増大のリスクを懸念することなく経営に専念することができるようになります。
上記ア、イは株式についての規定ですから、株式以外の会社の事業に供されている会社代表者名義の財産(例えば会社工場の建物や敷地が会社名義ではなく代表者名義とされていることも多いと思われます。)には適用されません。これら事業用資産も原則として遺留分減殺の対象となりますが、上記ア、イの合意と併せて、推定相続人全員の合意により、これらを遺留分算定の基礎財産から除外することが認められます。
これにより株式以外の事業用資産についても円滑な事業承継を実現することができるようになります。
上記❷の合意が効力を生ずるためには、当該合意の日から1か月以内に経済産業大臣に対して確認の申請を行って確認を受け、更にその確認を受けた日から1か月以内に家庭裁判所に申し立てを行って許可を受ける必要があります。