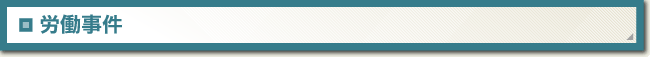
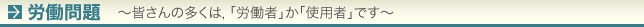
労働問題とは、労働契約関係について生ずる法的問題です。
基本的に、ある人がある人を「使用する」関係と、その対価として「賃金」を支払う関係があれば、そこには労働契約関係があると言えます。
その関係が、パートやアルバイトと呼ばれていても、労働契約関係であることに変わりはありません。
皆さんの内の大多数の方が、労働契約関係の一方当事者(「労働者」または「使用者」)であることがお分かり頂けると思います。
ここでは、「労働者」の立場から、お話をさせて頂きます。

労働契約も契約ですので、契約において両当事者が合意した内容が、その労働契約関係におけるルールとなるのが原則です。
ただ、労働契約関係においては、労働者保護を図りつつ、労働者と使用者の利益を調整する見地から、労働基準法をはじめとする法律、「労働協約」、「就業規則」が、労働契約に対して効力を及ぼすこととされています。
この内の「就業規則」が、労働者にとっては一番身近なルールと言えるでしょう。
法律上、常態として10人の労働者が使用されている職場においては、使用者は就業規則をが作成しなければならないこととなっています。
労働時間(残業)、休憩時間、年休、賃金等、疑問に思うことがあれば、職場の就業規則を確認してみてはいかがでしょうか。

ここでは、労働者にとっては一番重大な危機である解雇について、問題点等をお話したいと思います。
ある人がある人を雇う必要がなくなったとき、雇いたくなくなったとき、契約が自由であるという発想からは、自由に解雇ができることとなりそうです。
しかし、労働契約関係においては、労働者保護の見地から、使用者が労働者を解雇する場合には、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされています(労働契約法第16条)。
「客観的に合理的な理由」とは、勤務成績の著しい不良、職場規律違反、人員整理の必要等であり、「社会通念上の相当性」とは、上記の「客観的に合理的な理由」の程度、解雇回避の手段の有無、労働者側の事情等を考慮して、解雇もやむを得ないと判断されることを意味します。
これらの要件は、結局はケースバイケースの判断ですが、裁判例からは、容易には認定されない性質のものであることが理解できます。
例えば、勤務成績の不良といっても、それまでの勤務実績に照らして、企業経営に支障を生ずるなどして企業から排斥すべき程度のものであるかといった絞りがかけられるのが通常であり、また、解雇ではなく、他の処分(減給、配置換え、教育指導等)によることはできないのか、解雇に先だって、それらの処分は行われたのかといった絞りがかけられるのが通常です。
その結果、前記の要件が否定され、解雇が無効となることも十分に考えられます。
①で述べたことからすると、なぜ解雇を行ったのかという使用者の意図を把握することが大切であることが分かると思います。
この点に関し、労働者は使用者に対し、解雇理由の証明書の交付を求めることができます(労働基準法第22条2項)。
解雇の効力を争い得るか、弁護士等に相談する場合にも役立ちますし、使用者の側に解雇理由の「後出し」を許さないためにも、解雇がなされた場合には、この証明書を請求しておくべきでしょう。
解雇に「客観的に合理的な理由」や「社会通念上の相当性」が認められないと解される場合には、解雇の無効を確認し、無効な解雇により働けなかった期間についての賃金を請求する訴訟を提起することが考えられます。
また、近年、訴訟よりも比較的早期に事件を解決できる仕組として、労働審判制度も整備されたところです。これは、基本的に3回程度の期日で、第一次的には話し合いによる解決を目指す制度であり、概ね常識的な解決がなされるものと認識されています。
また、弁護士が、使用者に対し、法的問題性を指摘することにより、裁判等を経ないで、通常の話し合いにより解決に至ることもあります。
解雇の正当性に疑問を感じた場合には、弁護士に法律相談をし、事案に適した解決方法を検討するのがよいでしょう。
仮に、解雇の正当性は認めざるを得ない場合でも、「解雇予告手当」を請求する余地はあります。
「解雇予告手当」とは、解雇された労働者の再就職活動をし易くする見地から、使用者が支払わなければならないとされている金銭のことです(労働基準法第20条1項)。使用者が労働者を即時に解雇する場合には、原則としては、30日分の賃金を支払わなければならないこととなります。
解雇を受け入れざるを得ないと思う場合でも、解雇予告手当の請求は検討してみる必要があるでしょう。

労働事件は解雇事案に限られるものではありません。その他にも、「使用する」、「使用される」という継続的人間関係の中で、様々な問題が生じ得ます。
それらの問題は、解雇等の、いわば決裂の状態に至っていない段階での問題と言えますので、第一次的には、使用者と労働者との信頼関係の中で解消されることが望ましいでしょう。
しかし、使用者の意識の持ち方も様々であり、労働者としては、裁判等の法的手続を検討せざるを得ない場合もあるでしょう。
この様な場合にも、法律相談を御利用頂ければと思います。